
ジュエリーリフォーム
想い出のあるジュエリーを次世代へ

ジュエリーの修理
熟練の職人による確かな技術

オーダーメイド
世界に一つ、あなただけのジュエリー

時計の修理
電池交換からオーバーホールまで
1978年に創業して以来、年間で約10000件以上のジュエリーリフォームとオーダーメイドジュエリーの加工実績があります。 当工房は、日本で唯一の「英国宝石学協会特別公認企業」であり、宝石学のプロフェッショナルな集団です。
Recommend
2019年公開の映画『コンフィデンスマンJP』ロマンス編 今回は、香港を舞台に史上最大のターゲットである世界最高のダイヤを巡って壮大なドラマが展開されます。この世界最高のパープルダイヤのネックレスのデザイン、制作を夢仕立が担当させていただきました。
日テレ「午前0時の森」にジュエリーの専門家として磨き、仕上げのプロフェッショナルとして出演しました。生放送の出演なので時間との勝負でしたが、ジュエリー磨きを楽しんでいただけました。
今回は取材で受けたジュエリーリフォームの工程をご紹介いたします。(2021年10月24日放送)

『やんごとなき一族』の原作に登場するカフスを元に、番組の美術デザイナーが描いたデザインを基にして、実際のカフスを製作しました。お客様からのご要望は、デザイン画と比較して大きな違いが出ないようにすることでした。そのため、基本形は元の形状をそのまま使用しました。

「梨本宮さま下賜のジュエリー」3点無事修復が終わり納品させて頂きましたので、差し支えない範囲で当初の状況、途中経過、完成と課程をお話しさせて頂きます。
Features
お預かりしたお品物は、運送中、加工中、保管中、全ての行程において保険が適用されます。これは夢仕立のみに適用が認められた保険で、他社での適用はございません。
お預かり時に顕微鏡カメラで宝石の特徴を捉え、宝石の入れ違い、すり替わり、加工の際に傷をつけてしまうなどについて、安心していただくことができます。
Jewelry reform
お母様にもらった立爪のエンゲージリングや、思い入れはあるけれど使われていない宝石や地金を利用して、リーズナブルな価格でオリジナルデザインのジュエリーにリフォームする事が出来ます。

立爪のダイヤモンドは、リフォームをご相談される中でも最も多いジュエリーです。

石の留まっているトップの部分はそのままに、金具だけを付け替えることでお手軽なリフォームが可能です。

金、プラチナ、ロジウムメッキなどお手持ちのジュエリーにメッキ加工する事によってジュエリーの雰囲気を一新。
「材料費も含めた金額ですか?」よくお客様からのお問い合わせで、このようなご質問を受けます。工賃のみのご提案をすると一見安く見えますが、実際には材料費と工賃が必要になります。夢仕立では全て含めた金額しかお伝えしませんので、後で料金が追加される事はありません。
Jewelry repair
大切な人から贈られた思い出の品、親から代々受け継いだものなど、お客様の歴史と共に歩んできた貴重なジュエリーを可能な限りご要望の形に修理し、現状で最高の状態に仕上げます。アクセサリー、ジュエリーの修理、指輪のサイズ直し、ネックレスのチェーン切れ、宝石が取れた、ブランド品の修理、クリーニングなどお任せください。
修理のご依頼で最も多いご相談が「リングのサイズ直し」です。石が付いているものや表面に彫金が施されていたり模様の入っているリングは、サイズ直しを行うと同時に、そのデザインを復元させる必要があります。この工程は職人の中でもかなりの熟練者でなければ行うことが出来ません。「夢仕立」に在籍している職人は熟練者ばかりですので、この様な困難な加工でもお引き受けすることが出来ます。
「夢仕立」ではこれまでにティファニー、カルティエ、ブルガリ、ハリーウインストンなどの数々のブランド品の修理も取り扱ってまいりました。修理が難しく他のお店で断られてしまった物でも是非、一度ご相談下さい。
「ネックレスのチェーンは、簡単に切れてしまうもの」ネックレスのチェーンが切れたり、引き輪やプレートとチェーンをつなぐ部分の丸カン壊れてしまった場合はロー付け修理を行います。何かに引っ掛けてしまった時、洋服を脱ぐ時、小さなお子さんが引っ張ってちぎってしまったなどなど。ネックレスの修理で一番多いお問い合わせはチェーン切れ修理です。
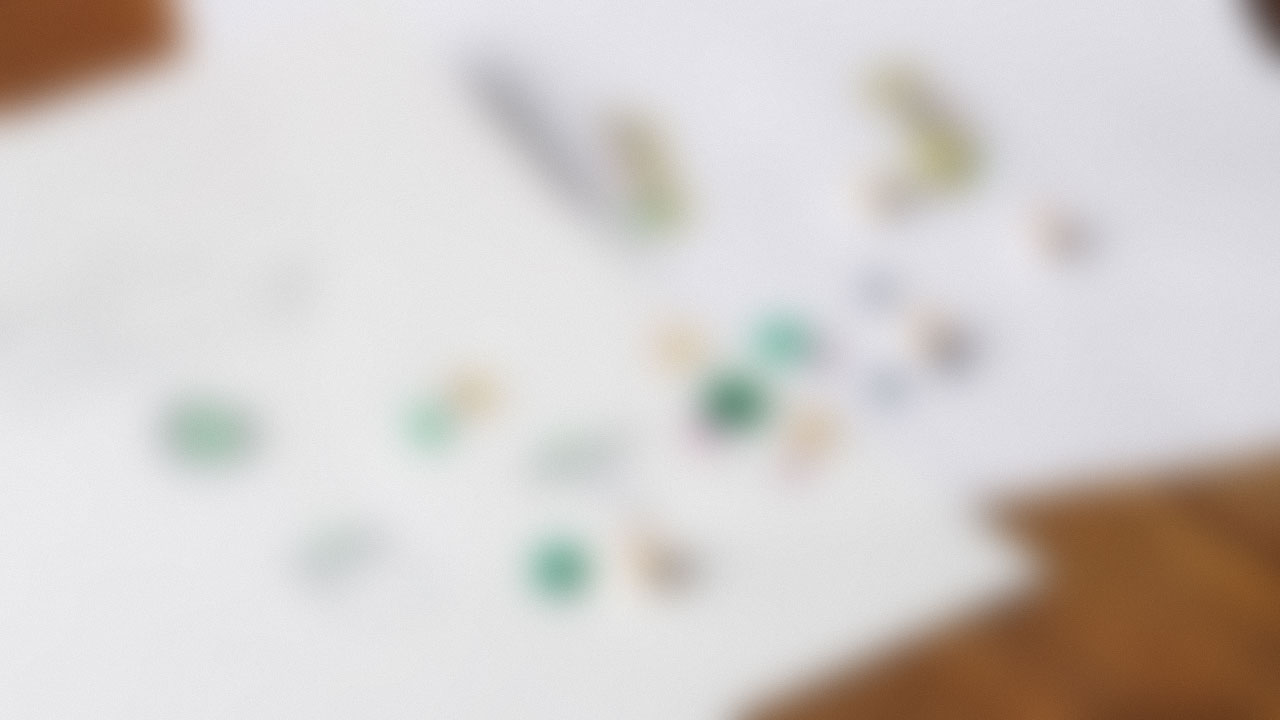
Ordermade jewelry
自分の足で素敵なジュエリーを探すのも楽しいですけれども、自分が想像した世界にただ一つだけのオリジナルジュエリー、オーダーメイドのジュエリーが欲しいと思った事はありませんか? お打ち合わせにてイメージを固めてデザイン画から製作し、ご納得いただけるまでご提案致しますのでご安心ください。憧れのジュエリーの再現や、世界に一つだけのオリジナルのジュエリーを製作が可能です。ご予算に合わせてご提案致しますのでお気軽にごお問い合わせください。

これから共に歩んでいく二人にとって、その絆の証である「結婚指輪」はこだわって選びたいものですよね。 二人が納得する結婚指輪を選ぼうと、色々なお店を巡り歩き、気に入るものを探しても、なかなかスムーズにはいかないもの。そんなときは、妥協して選ぶのではなく、オーダーメイドジュエリーだからこその「特別な結婚指輪を作る」という選択肢があります。
2019年公開の映画『コンフィデンスマンJP』ロマンス編 今回は、香港を舞台に史上最大のターゲットである世界最高のダイヤを巡って壮大なドラマが展開されます。この世界最高のパープルダイヤのネックレスのデザイン、制作を夢仕立が担当させていただきました。

Pearl necklace thread Longe

その最大の特徴は「切れにくい」「パールネックレスを洗える」ということです。 パールは洗うことにより限りなく劣化を抑えることができます。 高品質パールネックレスほど、ロンジェシステムの価値を最大限生かすことができるため、鑑別技術によって選別した最高品質のパールにロンジェシステムを施したネックレスが「ロンジェ・パールネックレス」です。
パールネックレスの糸変え
パールネックレスの水洗い / 真珠は水洗い出来る
Trade-in and purchase of bullion

当社で下取り買取が出来る金属はプラチナ、金、銀(洋銀を除く)です。 (但し銀は10gからとさせていただいております。) お持ちいただいた日の地金相場に基づいて行います。 買い取りのみの場合にはお手数ですが保険証、免許証等、身分証を拝見させて頂いております。
Customer reviews
評価 : ★★★★★
丁寧に対応いただきました。 理想のデザインをイメージしやすいようにすでにある商品を見せていただき、想像しやすかったです! なるべくダイヤの高さを出さないように、等細かな依頼も対応いただきました。 できあがりも理想通りで驚きました😭✨ ありがとうございました。 一生物、大切に使います。
評価 : ★★★★★
母から譲り受けた古いダイヤの指輪をリフォームして頂きました。デパートの中ということで安心感もあり、お店の方の対応も親切で良かったです。 ずっと引き出しの中に眠っていましたがこれからたくさん身につけたいと思います。
評価 : ★★★★★
高齢の母が指輪はしなくなり、そのまま放置ではもったいないので、指輪からネックレスにリメイクしました。 とても綺麗な仕上がりで満足です! 眠っていた宝石が使いやすいものに変えていただき母も喜んでいます。
評価 : ★★★★★
イヤリングをピアスにリフォームしていただきました。丁寧に対応してくださり安心してお願いできました。間近に控えた友人の結婚式にも間に合い感謝です。 引き続き立爪ダイヤモンドリングをリフォームしていただきました。今回も安心してお願いすることができました。気軽にする機会が増えそうで楽しみです。
評価 : ★★★★★
この度、39年前の婚約指輪をリフォームしていただきましたが、高さを抑えていただくといった希望通りだけでなく、予想を越える出来上がりで大満足です。
評価 : ★★★★★
祖母の形見の帯留を、鑑定からリフォームまでお願いいたしました。丁寧に相談に乗ってくださり、気持ちに寄り添ってデザインの提案してくださり、思わず涙が溢れました。完成後は更に美しく、今後もずっと大切にしたいと思います。こちらにお願いして、本当によかったです。
評価 : ★★★★★
オーダーメイドで綺麗に仕上げていただきました。ありがとうございます。
評価 : ★★★★★
ジュエリーリフォーム、ジュエリーの修理、オーダメイドジュエリーと言ったらここ、という位有名なお店です。 まだジュエリーリフォームが一般的ではなかった40年前からやっている老舗店でありながら、新しい技術もどんどん導入しているらしく、どこでも受け付けてもらえない修理も引き受けてくれます。 また私は修理とか洗浄とかでお世話になっていますが、「数年前には修理不可だったものができるようなりました」とわざわざ連絡してくれたりもする、とっても親切なお店です。 全店舗に国際的な鑑定資格である英国宝石学鑑定士の方がいらっしゃるので、安心してジュエリーを預けられます。 他のお店に行くよりも、まずここに行くことをオススメします!!
評価 : ★★★★★
今回はお直しとオーダーメイドの指輪2本をお願いしました。お直し等はいつも夢仕立さんにお願いしていて、毎回希望通りに丁寧に仕上げてくださるのでとても嬉しいです。今回もありがとうございました。
評価 : ★★★★★
長年 母が大事に閉まっていた指輪を想像以上に綺麗にして頂いて大変感謝しています。 変形していた部分の修復や欠けていたダイアモンドも取り寄せて頂いてまるで新品のような輝きを取り戻すことができました。窓口の方も対応が非常に丁寧で安心して任せたいと思えました。ありがとうございました。
評価 : ★★★★★
今回初めて伺いました。真珠の糸の交換をお願いしました。長さの調整も丁寧にしていただきました。ありがとうございました。